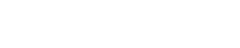従業員エンゲージメント
推進体制
JSRグループでは、従業員エンゲージメント調査をCHROが管掌する人財開発部主導の下で実施しています。調査結果は、各社・各拠点・各部門長を通じて従業員へフィードバックされます。さらに、各社・各拠点・各部門における調査結果の要因分析や改善活動は人財開発部を通じて、各担当役員へ報告されます。
基本的な考え方/方針
JSRグループでは、従業員エンゲージメントの向上が、企業活動を持続し企業価値を高めていくための鍵になると考えています。そのため、定期的なアンケート調査により、従業員の声を拾い上げ、エンゲージメントの測定に努めています。得られたアンケートの結果に基づき、各組織において取り組みを進めています。さらに、グループ全体としても、多様な考えや背景を持つ従業員の働きがいと働きやすさをサポートするために、各種制度・施策の拡充に努めています。
指標と目標
- 1.JSR株式会社では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、女性の職業生活における活躍推進行動計画(第4期目:2023年4月1日~2026年3月31日)を策定しています。
| 目標 | 2026年3月31日までに女性管理職比率7%を達成する。また、新卒総合職採用における女性比率について、事務系は50%・技術系は30%を達成する。 |
|---|
| 実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 集計対象拠点 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 女性従業員採用比率 (大学卒技術系) |
JSR株式会社 | % | 26 | 30 | 17 | 11 | 16 |
| 女性従業員採用比率 (大学卒事務系) |
JSR株式会社 | % | 55 | 60 | 100 | 40 | 75 |
| 女性管理職比率 | JSR株式会社 | % | 4.2 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
- 2.次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、次世代育成支援対策行動計画(第9期目:2023年4月1日~2026年3月31日)を策定しています。
| 目標 | 2026年3月31日までに男性従業員の育児休業取得率を80%とし、平均取得日数20日以上を達成する。また、従業員の年次有給休暇の取得率80%以上を維持する。 |
|---|
| 実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 集計対象拠点 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 男性従業員育児休業取得率 | JSR株式会社 | % | 50.9 | 72.7 | 81.3 | 89.2 | 85.5 |
| 男性従業員育児休業平均取得日数 | JSR株式会社 | 日 | 19.6 | 19.2 | 20.7 | 33.7 | 39.5 |
| 年次有給休暇取得率 | JSR株式会社 | % | 81.0 | 87.4 | 88.8 | 91.1 | 84.1 |
取り組み
1.従業員エンゲージメント調査
JSRグループでは、従業員エンゲージメントサーベイを実施し、会社や部署単位などで各組織のエンゲージメント状況や課題を可視化しています。組織ごとに状況が異なるとの考えから、サーベイ結果は各組織へ迅速にフィードバックし、組織ごとに重点課題を整理し、アクションプランの策定・実行をしています。さらに、JSR株式会社の人財開発部を中心とし、グループ共通の傾向や課題を全社的な施策設計・見直しに反映しています。
2.働きやすさの促進
JSR株式会社では、働きやすさの向上に向け、制度・インフラの整備と、風土醸成の両輪で取り組みを進めています。
(1)各種施策・制度の整備
女性の活躍推進
活躍機会の拡大や成長支援、環境整備を通じて、女性の活躍を継続的に推進しています。管理職向けマネジメント支援(アンコンシャス・バイアスの理解やマイクロアグレッション防止など)、社外研修(J-Win 等)派遣、ロールモデル講演会、本人・上司ヒアリングによる課題抽出と施策反映を継続しています。詳細はpdfをご確認ください。
ライフステージ
育児・介護・治療など多様なライフイベントとの両立を支える制度・インフラを整備しています。育児関連では、産前産後休暇、出生時育児休業、配偶者出産時の特別有給、育児休業、小6修了までの短時間勤務などを、看護・介護に関しては看護・介護休暇、介護休業などをそれぞれ整備しています。また、休業中も希望者は会社貸与PCや専用アプリから社内イントラネット掲載の広報誌や福利厚生制度の詳細など、社内情報へアクセスできる仕組みを提供しています。詳細はpdfをご確認ください。
キャリア
各人のキャリアステージに応じた就業機会の拡大とキャリアの継続性を支える制度・施策を整備しています。休職者・退職者向けには、キャリア再開制度や配偶者海外転勤時休職制度など、JSR株式会社での再雇用を可能としています。また、若手向けのメンタリングを導入し、自部署以外の先輩社員との関係づくりを通して、さまざまな悩みを相談できる場を提供しています。その他制度や詳細はpdfをご確認ください。
(2)マインドセット・風土の醸成
JSR株式会社では、従業員一人ひとりが制度を有効に活用できるよう、各種制度に対する理解を促しています。多様な人財/多様な働き方を紹介する取り組みとして、社内イントラネットに男性の育児休業や介護・治療と仕事を両立している従業員へのインタビューを掲載しています。また、階層別研修やe-learning等の社内教育を通じて、制度の趣旨や期待する行動の浸透を図り、労使双方の意識と行動変容を後押ししています。