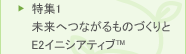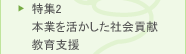2011年は、歴史的なターニングポイントになる年であろう。日本だけでなく、世界のさまざまな価値観が変わるように思える。
しかし、これまでのグローバル化の大きな流れまでが変わるのか。それとも、グローバル化の流れは変わらずに、本質的な問い、例えば、人類にとって「経済」とは何なのかに対して答えを出すようになるのか。日本から何を発信するのか。これが大きな意味を持ちそうである。
何を変えるべきなのか。長期的な展望に基づく投資が必須である製造業を基盤とするこの国に、米国流の経営方針を持ち込んで、「短期的合理化」と「立ち止まらない改善」を合言葉になんとかやってきたが、かえって、一部では脆さが目立ち、結果的に、東日本大震災の自然の力を真正面から受け止めることはできなかった。余りにも大きな力は、やはりしなやかに受け流すことも必要だということを思い知ったのではないか。
本題に戻って、CSRレポートを読むとき、トップの意思の表明がもっとも重要である。今回は、「成長への始動」、「変わらないもの」を示す企業理念、「E2イニシアティブ」、「自由と規律」の企業文化、この4項目を中心に意向が述べられている。
環境・エネルギー関係である「E2イニシアティブ」については、別途コメントさせていただいているが、企業経営にとって環境が必然的な境界条件になっており、真摯に取り組む姿勢が示されている。
環境は公共性の高い分野であり、通常にも増して「安価で良い製品」が求められているという認識のもとに、新たなニーズを把握し、積極的に取り組むとのメッセージであり、まずは普及を考える立場からは、正当な取り組みだと判断できる。
しかし、さらに言えば、環境分野を牽引するには、先導的かつ先鋭的であるゆえに、やや高価であるが顧客満足度が高いといった製品の開発が必須であることも認識されていると信じたい。
個人的な見解だが、環境製品を普及させるには、性能と価格がプレミアム級のもの、トップクラスのもの、普及クラスのもの、という3段階での選択ができることが、今後の方向性であろうと考えている。
環境関係のほかの活動をチェックすると、まず、「生物多様性」が目についた。経営計画の中にも組み込まれており、いわゆる「着実な進展」のレベルを超す、速やかな対応が実現できていることがわかった。
実は、2010年の第三者意見で「生物多様性」にどのように取り組むか注視させていただくと書かせていただいた。名古屋で開催されたCOP10の成功によって、企業の意識が全般的に向上したが、JSRにおいては、いささか驚くほどのスピードでの対応である。
そのほかの項目では、出前授業が素晴らしい。最近、複雑になり過ぎた製品の仕組みを小学生が理解することは、将来への消費者教育であり、したがって投資でもある。受験対応ばかり考える教育界への刺激になることだろう。
小学生だけでなく、中学生を対象とした取り組みもあるようなので、興味を引きそうな次世代デバイスに関する題材での出前授業もできないものだろうか。
最後になったが、CSR調達の運用が開始されたことにも注目すべきだと思う。自らの企業倫理や環境の基準が、サプライチェーンを通じて、他の企業にも伝搬するというこの仕組みが、今後、どのような効果を生み出すのか、まさに興味津々である。しばらく観察させていただきたいと思う。