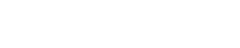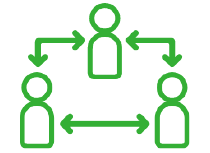サステナビリティ
企業活動を通じた価値創造により、
持続可能な地球環境や社会の実現に貢献します
事業活動を通じた社会への価値提供
価値を提供し続けるための
経営基盤強化
サステナビリティ最新情報
- 2025年05月12日
- 温室効果ガス(GHG)排出量の第三者検証を受審
- 2025年02月28日
- 「CDP2024」の「気候変動」「水セキュリティ」2分野でB評価を獲得
- 2024年10月30日
- サステナビリティサイトをリニューアルしました。
- 2024年06月05日
- 2022年度のGHG排出量実績に対する第三者機関による検証意見書を掲載しました。(PDF:0.8MB)
- 2024年04月24日
- 2024年台湾東部沖地震に対する被災地・被災者支援について
- 2024年01月24日
- 令和6年能登半島地震被害に対する被災地・被災者への支援について
- 2023年04月01日
- JSR、日本気候リーダーズ・パートナシップ(JCLP)に賛助会員として加盟致しました。
(日本気候リーダーズ・パートナーシップ HP) - 2023年03月01日
- トルコ・シリア大地震による被災地・被災者への支援について